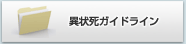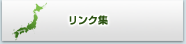日本法医学会法医認定医・死体検案認定医
資格認定試験受験の手引き
1 法医認定医資格認定試験
2 死体検案認定医資格認定試験
3 受験申し込み方法と試験の日時・場所・出願期間
4 資格認定試験の出題方式
5 資格認定試験の合否判定
6 結果の通知および資格の認定
7 その他
2 死体検案認定医資格認定試験
3 受験申し込み方法と試験の日時・場所・出願期間
4 資格認定試験の出題方式
5 資格認定試験の合否判定
6 結果の通知および資格の認定
7 その他
1 法医認定医資格認定試験
- 法医認定医の申請をする者は次の条件を満たさなければならない。
- 日本国の医師免許を取得していること。
- 死体解剖保存法による死体解剖資格を取得していること
- 申請出願時において3年以上継続して日本法医学会会員であり、かつ入会以来の会費を全納していること。
- 法医認定医研修施設(別表1)に4年以上在籍して法医学の研修を修了し、その期間中に200体以上の死体検案ないし法医解剖(いずれも補助を含む)の経験を有する者。ただし、そのうち法医解剖は60体以上であることを要す。法医解剖数は初期臨床研修期間後に行った法医解剖数とする。
- 法医学に関する5回以上の学会報告及び5編以上の論文(原著、総説、症例、技術報告)又は著書があること。
- 自身の所属する大学法医学教室教授あるいは監察医務を行う機関の長の推薦があること。なお申請者が機関の長である場合は自薦でよい。
- 医事に関して罰金以上、その他に関しては禁錮以上の刑に処せられた者でないことを要する。
- 出願時に提出する研修に関する書類は以下の通りである。
- 法医研修実績の明細(様式3-1)
研修期間中に行った、死体検案・法医解剖200例以上についての、解剖年、 施設名、剖検・検案の別、剖検(検案)番号、解剖体の年齢・性別、死因 の一覧。 - 業績目録(様式2-1、2-2)
研修期間中に発表した法医学に関する原著論文(5編以上)、 学会発表(5回以上)の一覧。 - 原著論文は、著者:論文題名。 学協会誌名、巻、始めと終わりのページ、発行年。の順に記載する。
- 学会発表は演者:演題。学会名、発表年。の順に記載する。
上記研修に関する書類は合否判定の資料になる。
2 死体検案認定医資格認定試験
- 受験資格は下記のすべてを満たす者である。
- 日本国の医師免許を取得している者。
- 申請時において日本法医学会会員であり、 かつ入会以来の会費を全納している者。
- 4年以上死体検案(法医解剖の執刀あるいは補助を含む)に従事し、 かつ50例以上の死体検案の経験を有する者。
- 法医学に関する1回以上の学会報告、または1編以上の原著論文が ある者。
- 以下のいずれかの方法において、法医学に関する研修を終了した者。
- 大学法医学教室あるいは監察医務を行う機関に2年以上在籍して 法医学の研修を行った者。
- 日本法医学会が指定する研修会に出席するなどして、 規定以上の単位(5単位または4単位)を取得した者。
- 医事に関して罰金以上、その他に関しては禁固以上の刑に 処せられたことがない者。
- 出願時に提出する研修に関する書類は以下の通りである。
- 死体検案実績の明細(様式2-1)
出願時までに行った、死体検案(法医解剖の執刀あるいは補助を含む) 50例以上についての検案(剖検)年月、検案実施地または剖検実施施設、 検案・剖検の別、検案(剖検)番号、年齢、性、死因の一覧。 ただし検案(剖検)番号がない場合はこれを省略できる。 - 業績目録(様式2-1、2-2)
出願時までに発表した法医学に関する原著論文、 学会発表(1回以上)の一覧。
原著論文は、著者:論文題名。 学協会誌名、巻、始めと終わりのページ、発行年の順に記載する。
学会発表は演者:演題。学会名、発表年。の順に記載し、 抄録(演題要旨)のコピーを添付する。
- 死体検案認定医制度研修会参加証明書
日本法医学会が指定する研修会に出席して研修を終了した場合は、 死体検案認定医制度研修会参加証明書を提出する必要がある。
上記研修に関する書類は合否判定の資料になる。
3 受験申し込み方法と試験の日時・場所・出願期間
- 受験申し込み書類の請求方法
受験を希望するものは、受験申し込み書類を「法医認定医および死体検案認定医の受験出願について」ページよりダウンロードするか郵便で請求すること。
- 受験申し込み書類の提出方法
- 法医認定医資格認定試験
- 法医認定医申請書(様式1)
- 業績目録(様式2)
- 法医研修実績の明細(様式3)
- 医師免許証(写し)
- 死体解剖資格認定証明書(写し)
- 研修指導者の推薦状
- 監察医委嘱状(写し。監察医務を行う機関の長による推薦の場合)
- 審査手数料(受験料)を納入した振替払込票の写し
i~viiiを3部(2部はコピーでよい)一括して送付すること。
- 死体検案認定医資格認定試験
- 死体検案認定医申請書(様式1-1)
- 業績目録(様式1-2)
- 死体検案実績の明細(様式2)
- 死体検案認定医制度研修会参加証明書
- 医師免許証(写し)
- 監察医委嘱状(写し。監察医務を行う機関の長による推薦の場合)
- 審査手数料(受験料)を納入した振替払込票の写し
i~viiを3部(2部はコピーでよい)一括して送付すること。
- 受験料
法医認定医・死体検案認定医 各 20,000円(平成14年度)
- 受験申し込み書類の請求・提出先
〒112-0012 東京都文京区大塚4-21-18
東京都監察医務院内
日本法医学会 認定医制度運営委員会
E-mail:leg-med.info★blue.ocn.ne.jp
※上記の「★」は「@」に置き換えてください。
TEL/FAX:03-3942-5246
- 出願期間
7月1日~8月19日
- 受験資格審査
受験資格審査の結果は9月中旬頃本人あてに通知し、受験票を送付する。
- 試験の日時
10月第4日曜日
- 試験場
- 法医認定医資格認定試験:年度ごとに決定
- 死体検案認定医資格認定試験:年度ごとに決定
4 資格認定試験の出題方式
- 法医認定医資格認定試験
- 問題形式および試験時間
- 客観問題(multiple choice question):60題(70分、120点)
- 論述問題:4題(法医領域の事項を簡潔に説明する。40分、80点)
- 法医実地問題(120分)
- 症例問題:2題(症例を提示し、所見およびその解釈等を問う。60点)
- 写真問題:20題(マクロ・ミクロの写真を示し、所見・診断等を問う。80点)
- 死体検案書作成問題:2題(60点)
- 問題の内容および範囲
ガイドラインを別に示す。 - 死体検案認定医資格認定試験
- 問題の形式
- 客観問題(multiple choice question):10題(20点)
- 論述問題:1題(法医領域の事項を簡潔に説明する。20点)
- 法医実地問題
- 症例問題:1題(症例を提示し、所見およびその解釈等を問う。20点)
- 写真問題:2題(外表の写真を示し、所見・診断等を問う。10点)
- 死体検案書作成問題:2題(30点)
- 試験時間
120分 - 問題の範囲
ガイドラインを別に示す。
5 資格認定試験の合否判定
- 客観試験、論述試験および法医実地試験の結果から総合的に判定する。
- 申請書類の審査のみで不合格となることもあるので、注意して 作成すること。
6 結果の通知および資格の認定
- 試験の結果は2月頃郵送にて本人に通知する。
- 試験に合格したものは認定証交付時(3月)に資格認定料 (金30,000円(平成14年度))を納入すること。
7 その他
受験資格について不明な点がある場合は法医学会事務所まで問い合わせること。
日本法医学会認定医制度運営委員会